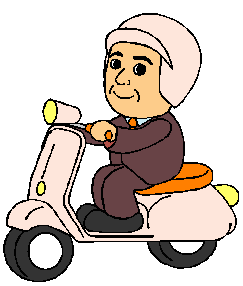| 不動産査定 |
「不動産査定」というのは、その不動産の現在の価格を見積もるということになる訳ですが |
|
業者が提示する「査定価格」には、いくつかの種類があります。 |
|
|
|
(1) すぐに売買が成立する価格(見込み客がいる場合の価格や買取価格など) |
|
(2) 現在の市況から考えて、短期間で成約する確立が高い価格(相場の下限) |
|
(3) 現在の市況から考えて、時間はかかっても成約する可能性がある価格(相場の上限) |
|
(4) 依頼者が満足・納得しそうな価格(相場より高いのでそのままでは売れない) |
|
|
|
数社の業者に査定を依頼して価格に差が出るのは、上記のように意味あいがバラバラなのと |
|
業者の経験・実績の違いから出るものです。 |
|
高い金額を提示する業者が良い業者とは限りません。ご自身の計画を提示したうえで |
|
査定を依頼し、細かい説明を聞くことが一番大切なことです。 |
|
|
| 取引態様 |
不動産業者が、お客様との間でどのような立場で不動産の取引を行うのかを示すものです。 |
|
|
|
(1) 仲介(媒介)・・・・・・成約時に仲介手数料が発生 |
|
(2) 代理・・・・・・・・・・・成約時に代理手数料が発生 |
|
(3) 売主(買主)・・・・・・手数料は発生しません。 |
|
|
|
仲介とは、一般的な取引形態で売りたい方と買いたい方の間に入って、取引を成立させます。 |
|
代理とは、依頼者より代理権を授与され依頼者に代理してすべての取引を成立させます。 |
|
売主(買主)とは、不動産会社自身が売主(買主)となり、相手方と直接取引するものです。 |
|
不動産広告等では、この取引態様を明示する義務があります。 |
|
折込広告などでは必ず記載されているはずですので、良く見てみてください。 |
|
|
| 任意売却 |
不動産をローンで購入している方が、そのローンの支払いができなくなったり、滞ったり |
|
した場合に、金融機関はある一定期間を経過した後に「競売手続き」に入ります。 |
|
つまり、担保を設定した不動産を売却して未払い分の貸付金を回収しようとするわけです。 |
|
これについては、正当な行為であり、債務者はこれを拒むことはできません。 |
|
|
|
金融機関が行う「競売手続き」は貸付金を回収するのが目的でありながら、現在の制度では |
|
一般取引価格より安く落札されることが多く、貸付金の回収が困難です。 |
|
そこで、金融機関によっては、「任意売却」という形式をとることがよくあります。 |
|
「強制的な売却」に対しての「任意な売却」と理解できるでしょう。 |
|
業者間では通称、「ニンバイ」や「ニンバイブッケン」と言います。 |
|
|
|
この任意売却は、債務者個人での取引は難しく、通常は金融機関・債務者・経験のある業者の |
|
詳細な打ち合わせにより行われます。もちろん合法なものであり違法行為ではありません。 |
|
金融機関・債務者にとっては競売価格よりも高く売れるメリットがあり、その物件を買う方には |
|
市況価格よりも安く買えるメリットがあります。 |
|
ただし、この取引には知識・経験・交渉が必要なため、買う方にとっては業者を吟味しないと |
|
思わぬトラブルを抱え込むことにも成りかねませんので、ご注意ください。 |
|
|
| 成年後見制度 |
高齢者社会を迎え、不動産を売却する方もご高齢の方が増えてきました。 |
|
マンションへ買い換えるため・施設へ入居するため・子供と同居するため等、理由は様々ですが |
|
最近は、特に増えてきています。 |
|
ご高齢であっても、ご本人がしっかりとしておられる場合は、何も問題はないのですが |
|
認知症の病気を抱えておせれる場合や、診断がなくてもその傾向が見られる場合には |
|
注意が必要となります。ほとんどの場合には付き添いのご家族が相談にみえられるのですが |
|
現在の法制度では、本人に有効な意思能力がないと認められる場合などには、たとえご家族で |
|
あっても代理人などになって不動産の売却(法律行為)を行うことは出来ません。 |
|
|
|
正式には、家庭裁判所において、「成年後見制度」の利用を申請し、後見人等の指定を受け |
|
そのうえで、不動産売却についても更に申請し許可が出てからでないと不動産の売却が |
|
出来ません。この後見人等は、通常問題ない場合には同居の家族が指名されますが |
|
特殊条件のある場合には、第三者が指名されることもあります。 |
|
また、申請を開始してから許可が出るのでの間に、本人の面談や診察など色々な作業があり |
|
数週間から数ヶ月かかることもあります。 |
|
|
| 事故物件 |
通常、事故物件と言う場合は、建物やその敷地内で自殺・殺人・事故等で人が亡くなっている |
|
ことを言います。法律の規定では、こういった「忌避事実」を宅建業者は買主に書面をもって |
|
説明する義務があるとされています。 |
|
これらは、「心理的瑕疵」と言い、気になる人はとても嫌だし、気にならない人は全然気にしない |
|
というものになります。 |
|
問題は、この「忌避事実」は、何年前のものまで説明義務があるかということです。 |
|
これは、業者間や業界団体でも判断が分かれるところであり、実際の運用としては |
|
|
|
(1) 事故後に所有者が1回でも変わっていれば説明しなくて良い。 |
|
(2) 事故後10年以上経過していれば、説明しなくてよい。 |
|
(3) 状況にかかわりなく事実を知ったのであれば必ず説明しなくてはならない。 |
|
|
|
などと、さまざまな考え方があるようです。 |
|
ただし、質問されて知っている事実を告げないのは問題だと思いますので、気になる方は |
|
自分から、「忌避事実」があるかどうか確認されるのが一番良いと思います。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
今後も随時更新していきます。この欄にないことでもお知りになりたいことがあれば |
|
お気軽にお問い合わせください。 |